今日は今年初めての県外までの桐たんすのお届けでした。起床は午前5時。当然ながら辺りは真っ暗。昨日から雪の状態が気になっていましたが、この辺りは雪もなく安心して出発できました。
新津ICから磐越道でいわきJCTまで、途中、会津地方は雪がありましたがこの程度であれば余裕でした。その後、常磐道に入りひたちなか市まで向かいますがそこで少しハプニングが。

常磐道の日立中央PAでエンジン浄化を試みますがダメでした。
数日前に、愛車ハイエースの排ガス浄化のサインが点灯し、それに従いエンジンを浄化したのですがその後、今度はエンジン点検のサインが点灯したのです。翌日トヨタに持ち込み見てもらうと、「これ最近多いんですよね」と・・・。(これってリコールですよね)
部品もなかなか入らず、何も出来なくて今日の配達を強行したのですが、やはりそこは無謀でした。途中、急に出力がなくなりスピードが出なくなりました。トヨタに電話したら、止まりはしないけれど出力がなくなりますとのことでしたので、このまま走り続けることに。

すぐに一軒目のひたちなか市のM様の素敵なご自宅に小袖の和たんすをお届けさせていただきました。M様、そして、ご注文いただいたお母様のA様ありがとうごいました。
その後は、スピードの出ない車のアクセルを必死に踏み込み、常磐道を東京に向けて走ります。

そして二軒目の板橋区のO様のマンションに正午頃到着し、焼桐の整理たんすをお届けさせていただきました。O様、ありがとうございました。
ここでやっと、スピードの出ない車ですが帰路につけると安心しました。帰り道は止まらないことを祈りつつ、何とか工場まで走って来れました。ハイエースはこんな車じゃないはずなんですが、トヨタさん、お願いしますよ。
明日も全力で頑張ります。







































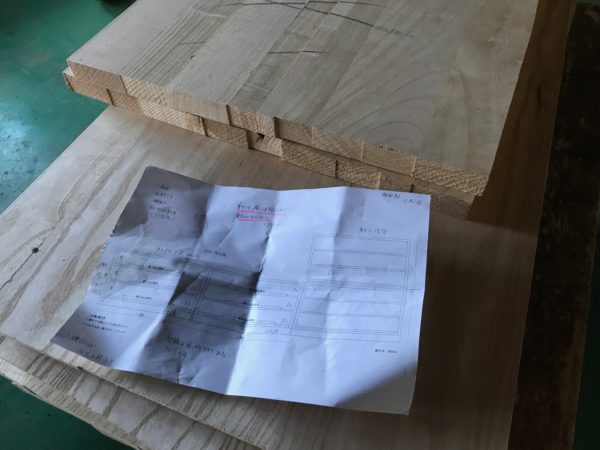











































最近のコメント