先週の土曜日に東京、神奈川まで桐たんすをお届けしたばかりですが、今日も、関東地方まで桐たんすのお届けに行ってきました。今日は弟ではなく色付け職人の石山君と一緒です。
起床は午前4時半、今日は奥様が早く起きたので私もつられて早めに起床です。石山君が工場に来るのを待って、午前6時に出発です。

今日の休憩はいつもの三芳ではなく、高坂SAで。
関越道→圏央道→東名→横浜新道と順調に走り、一軒目の戸塚区のお客様のマンションに予定通り午前10時に到着し、再生たんすをお届けさせていただきました。S様、ありがとうございました。

一軒目は再生たんすのお届けでした。
そして2軒目ですが今日の目的はここへのお届けでした。場所は言えないのですが、某博物館(正式ではないです。博物館としておきます)へ、国宝や重要文化財をしまうための桐たんすのお届けでした。
このたんすの依頼が来たのは昨年の2月。今から約一年前ですが、それから色々なやり取りをさせていただき、最終的に制作のOKが出たのが昨年の11月。それから段取りを始め、木取りをし、柾を組み、何だかんだで木取りだけで2ヶ月ほどかかりました。
幅は2尺9寸7分(約90cm)とそんなに大きくないのですが、奥行きは2尺2寸(約67cm)とかなり深め、高さは5尺7寸7分(約1m75cm)の三つに分かれる三つ重ねでの制作でした。

奥行きも深く、高さもある国宝や重要文化財をしまう桐たんす
浅めの引出しが12段と、少し深めの引出しが3段、数百年使えるようにとの事で、材料も吟味し、塗装はなしの木地仕上げ、引出しの取手も金属はダメとの事で、木の取手を探しました。

材料も吟味し、数百年使えるようにとの依頼でした。
石山君と2人でお届けしたのですが、かなりの重さで、二人でやっとで収めさせていただきました。
数年目にも関西地方の超有名な寺院にも、国宝をしまう収納たんす(たんすより大きいものでしたが)をお納めさせていただき、今回もこんなに重要なたんすをお納めさせていただきました。
職人として声がかかるだけでありがたいことです。
明日も全力で頑張ります。






































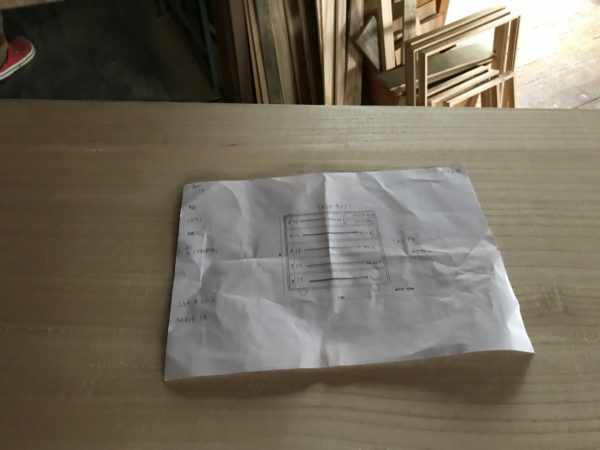

































最近のコメント