今日のお届けは、今年の年明けにわざわざ山形県から親子で桐の蔵の工場に来ていただき、和たんすと整理たんすをお求めいただきましたS様のご自宅まで、桐たんすのお届けに行って来ました。
緊急事態宣言が解除になったとは言え、県をまたぐ移動は自粛中ですが、今日のお届けは前々から決まっており、隣県という事でお届けに行って来ました。
出発は午前6時過ぎ。日本海東北道を新潟県の最後「朝日まほろば」まで行き、一旦、国道へ出て、山形県のあつみ温泉から再び日本海東北道を鶴岡まで。

そして約束の時間通りに、S様の素敵なご自宅へ、焼桐仕上げの小袖たんすをお届けさせていただきました。S様、ありがとうございました。
その後は、S様のお嬢様が住む寒河江市まで向かいます。

鶴岡ICから月山道路を経て山形道を走り寒河江市まで向かいます。S様のお嬢様、I様の素敵な新居へ、和たんすをお届けさせていただきました。

I様は、「いつもブログ見ていました。私のたんすが出来ていく日々を毎日見ていました」って言っていただきました。ホント、こんなブログですが読んで下さっているお客様からの反応は、本当にうれしいです。I様、ありがとうございました。
その後は、山形道から始めて走る東北中央道に入り、国道113号を走って新潟まで戻りました。
山形県は新潟県の隣県ですが、高速道路がまだ途切れ途切れで、なかなか行きにくい中、年明けに弊社まで来ていただきました事、本当に感謝です。
S様、I様、ありがとうございました。

















































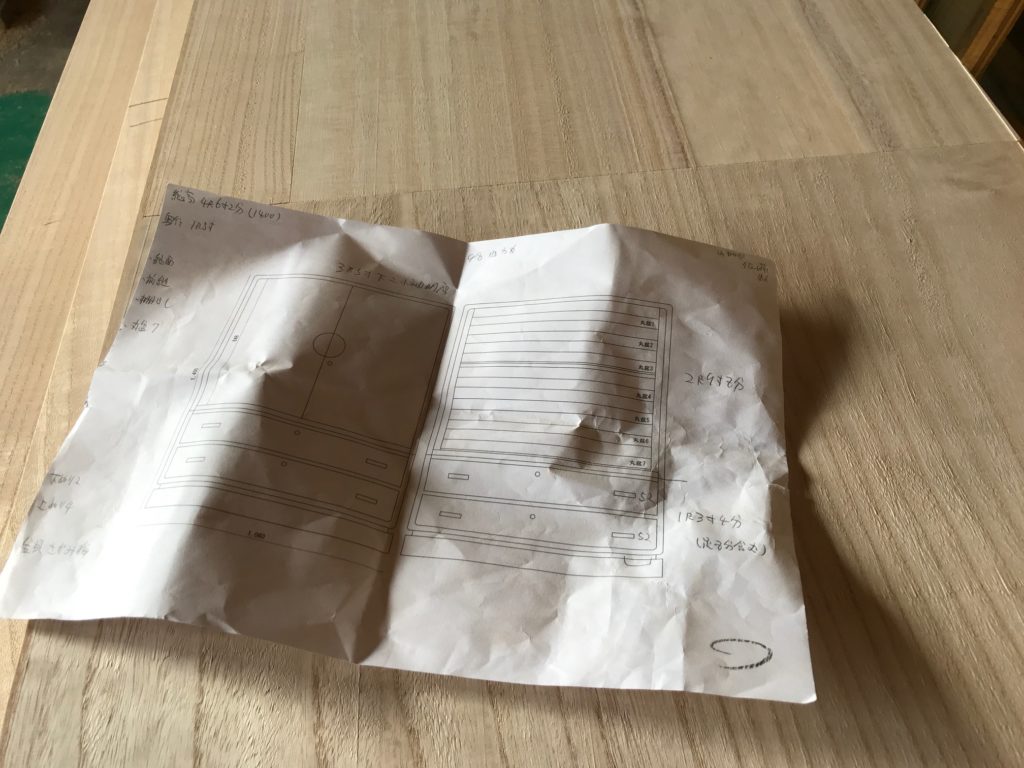






































最近のコメント