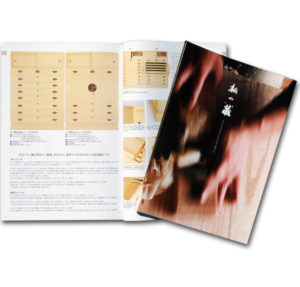千葉県S様からご注文いただきました和たんすの制作ですが、長いゴールデンウイークを挟みましたが今日が最後です。昨日は、小引き出しを本体に入れていくところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

本体に小引き出しを入れていきます。少しずつ入れていきながら当たっている場所を確認します。当たっていたらその場所を少しずつカンナで削り、また入れる。その繰り返しです。

下台の大きな引き出しも本体に入れていきます。引き出しを色々な角度で入れていき、当たっている場所がどこか?を確認しています。

当たっている場所を確認したら、出し手カンナで削っていきます。ここでも当たっている場所を確認し、出しては少しずつ削る。その繰り返しを何度も繰り返して、一つの引き出しを入れれば、他の引き出しが出てくるような、密閉度の高い引き出しが完成します。

引出しのホテ板(側板)を長台(台の長いカンナ)で削っていきます。引き出しがスムーズに入るように、本体にあたる場所を確認してそこをカンナで調整していきます。

引出しのどこが当たっているのかを確認しています。鉛筆で、当たっている場所に印を付け、そこをカンナで削り調整します。この作業を何度も繰り返し行っていきます。この作業は、良い桐たんすを作る命とも言うべきの作業です。

こうして引き出しを入れ終えると、観音開きの扉に移ります。扉を仕込み、カンナを掛けて仕上げると完成になります。
この後、塗装、金具付け、調整、検品、梱包を経て、お客様にお届けとなります。
今日は新潟市内まで桐たんす修理のご依頼で、修理する桐たんすの引き取りに行ってきました。数日前に背中を痛め、湿布を貼っての引き取りでしたが、再度、痛めてしまいどうすることも出来ず。病院行って来ます。