東京都O様から御注文頂きました和たんすの制作ですが、本体上台の裏板を木釘で打って止めていきます。裏板が美しいです。

木釘も配列もきちんとして、それだけで仕事の良さが出ています。木釘の配列と裏板の木目の良さ。自画自賛ですみません。

下台の地板をカンナで削って平らにしています。定規を当てながら平らになっているかを確認しています。

平らに削っていきます。

下台の外側の丸(本体四方)をカンナで削っていきます。手カンナで丸くしていくのも職人技です。

さすがに昨日からの新潟県は(全国的だけど)は暑いです。今日も、工場の二階は何度あったんだろう?
職人さん達の場所にはクーラーがあるからまだいいんだけど、私、朝一で板を貼っていたら汗でびしょ濡れ。
明日も相当暑いみたい・・・。




































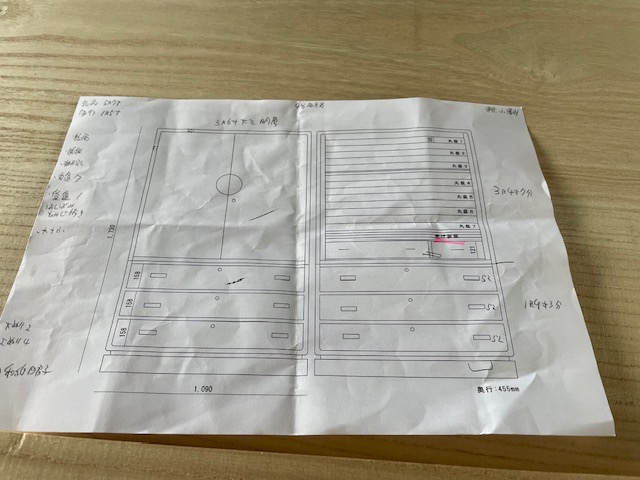














最近のコメント