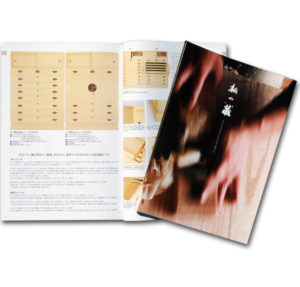愛媛県K様からご注文いただきました整理たんすの制作ですが、昨日は、地板に台輪を乗せ、寸法を見るところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

台輪の制作に入ります。胴丸という本体が丸い作りですので、台輪も同じように丸い作りになります。前面左右の両角を丸くするために、まっすぐにカットした面に丸くするための面木を貼っていきます。

本体に地板を付けるために、シャコ万とハタガネで地板を付けていきます。

本体を固め、裏板を木釘で打ったら、裏板をカンナで仕上げていきます。

整理たんす本体、立側を面取りの機械で丸く削っていきます。

機械で丸く削った後は、カンナを少しずつかけて丸くしていきます。

本体が完成したら、台輪の制作に入ります。本体がワイドなので、台輪もワイドになります。
台輪が完成したら本体が完成しました。

その後は、引き出し周りに入ります。引き出しのカガミ板(前板)を長台(台の長いカンナ)で削りながら、カガミを仕込んでいきます。(仕込むとは、引き出しが入る部分にカガミ板をピッタリ合わせていくことを、カガミを仕込むと言います)
引き出しを作るに際して使うケヒキ。

4つのケヒキを引き出しを作る時には使います。それぞれのケヒキの刃の位置は、いちいち動かさずに、その時専用に刃の位置が決まっています。

今日の私は板を切ります。各種、いろいろな板を切りましたが、はたまた4分板が少ないことに気づき、昨年干した板干場に板を見に行ったのですが、4分板がない。ちょっと考えます。
明日も全力で頑張ります。