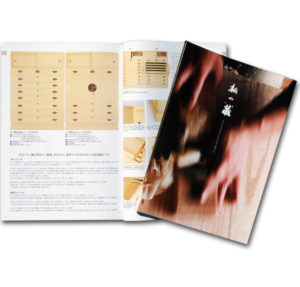埼玉県S様からご注文いただいております整理たんすの制作ですが、昨日は、台輪を作るところまでをお伝えしましたが、今日はその続きです。

引き出し周りに入っていきます。
引き出しの材料(ホテ板、先板、底板、カガミ板)を出してもらい、長さ切りでそれぞれの長さ、幅に切り分けていきます。

底板をカンナで仕上げていきます。幅の広い木目がしっかりした底板が美しいです。

先板の上面を擦り台に擦らせながら、長台(台の長いカンナ)で削っていきます。

カガミ板(前板)を仕込んでいます。
仕込むとは、引き出しの入る場所に、カガミ板を合わせていくことを仕込むと言います。

一番下の引き出しの内側の丸に合わせて、カガミ板の下もノミで丸くしていきます。

先板、ホテ板のホゾを取るために、昇降盤で切り込みを入れます。

切り込みを入れた先板を、ケヒキでホゾを取っていきます。
ケヒキの刃を油壷に付けながら、ホゾを取っていきます。

カガミ板とホテ板の蟻組みを取ります。

今日の私は、柾を組みます。

ご注文をいただいた桐たんすの柾を切り、親方から柾割をしてもらい、奥様から柾の目直しをしてもらってから(ここまででかなり手間かかっています)、やっと柾を組みます。
そして今日はFM新潟さんの取材がありました。

パーソナリティー(?)芸人さん(?)のヤンさんが工場に来て、カンナ掛けを体験されたり、いろいろなお話をさせていただきました。
この方、新潟ローカルだとは思うのですが、めちゃくちゃ面白い人ですね。

最後に全員で写真に入ってくれました。
ヤンさん、ありがとうございました!
明日も全力で頑張ります。